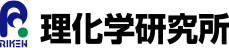文理融合のラボ・マネジメント
馬塚 れい子 チームリーダー(Ph.D.)
理化学研究所 脳神経科学研究センター 言語発達研究チーム
略歴
| 1981年 | 名古屋大学心理学部卒業 |
| 1983年 | 名古屋大学大学院心理学部修了 |
| 1984年 | エジンバラ大学言語学修士 |
| 1990年 | 米国・コーネル大学心理学部大学院博士課程修了 |
| 1989年 | 米国・デューク大学心理学部講師 |
| 1990年 | 米国・デューク大学心理学部Assistant Professor |
| 1997年 | 米国・デューク大学心理・脳神経科学部Associate Professor |
| 2013年-現在 | 米国・デューク大学心理・脳神経科学部Research Professor |
| 2004年 | 理化学研究所 脳科学総合研究センター(BSI) チームリーダー |
| 2018年-2023年3月 | 理化学研究所 脳神経科学研究センター(CBS) チームリーダー |
| 2023年4月-現在 | 理化学研究所 脳神経科学研究センター(CBS) 脳発達分子メカニズム研究チーム 客員主管研究員 |
プロジェクト説明
足立:本日はどうもありがとうございます。このプロジェクトのきっかけは、(前理事の)原山先生がエルゼビア・ファンデーションのボードメンバーでいらっしゃったということから、エルゼビア・ファンデーションからぜひ日本の女性研究者や若手研究者の支援ができるようなプロジェクトをやってみませんか、と言われて始めたものです。なので、本日はサイエンスのお話というわけではなくて、ラボマネジメントのお話。たとえば初めてPIになった方に参考になるようなお話を伺っていければなと思っております。よろしくお願いします。
馬塚:よろしくお願いします。
博士号取得前後
足立:馬塚先生のCVを拝見いたしまして、名古屋大学で学士号と修士号。それからエジンバラ大学でマスター、コーネル大学でドクターを取られていらっしゃいますけれども、学位を取られた時にどのような研究者といいますか、こういう研究室を持って、これから研究していきたいなぁみたいなご希望、当時の夢などありましたら、教えていただけますか。
馬塚:私の場合は発達心理学が専門なので、理科系の人とはだいぶルートが違いました。あの当時は発達心理学の人がポスドクをすることは滅多になくて、基本は博士を取ったらそのまま就職するというのが大半でした。なので、私もポスドクというのはやったことがなくて、Ph.Dの最後の年に博論を書きながら、応募書類を書いてそのまま就職したという感じです。初めてのポスドクというのはなくて、いつからPIなりたかったかというのもあまりなくて、要するに、就職することがそのままテニュアトラックの就職だったので、まあそんな感じで就職しました。
足立:そうすると、教員に就職するということですか。
馬塚:そうですね。大学の先生なので。私がたまたま就職したところがデューク大学というところで、アメリカでいうResearch Oneというカテゴリーに分類される大学なんですよね。Research Oneというのは先生方の評価というか、テニュアトラックの先生の評価は半分以上がリサーチで、後はティーチングとアドミニストレーションみたいな割合なんです。基本はPIとして外からお金を取ってきて、研究をしてというのが教官の評価ですので、ちゃんとリサーチをして論文を書かないとテニュアは取れない。まあその時点でラボを持っている、PIになったという、感じなんですよね。同級生で同じ時期に、例えばケミストリーとかエンジニアリングとかをやっていた人達は、もう既にポスドクをやるというのが前提になっていました。Ph.Dが終わったらポスドクを2年、3年ぐらいで2カ所ぐらい行って、その後就職っていう感じでした。我々は文系なので、Ph.Dが終わったらすぐ就職するというのが普通でした。今はもう発達心理学でもポスドクを2つ、3つやるというのは普通になってきましたけど、あの当時はそういう感じでした。
足立:そうすると、教員として採用された時にご自分のグラントなどで、すぐに人を雇われた感じですか。
馬塚:いえいえ。大学の先生になると、大学のお給料は出るけれども、大学からいわゆる研究費というのは出ません。あとは大学院生が来てくれるので、その大学院生と一緒に研究をするという感じです。最初からさすがに大きなお金は取れないので。でも、大学が、大学院生さんの授業料や生活費が賄える程度のお給料を出してくれるので、まあ学生さんと一緒に勉強しながらという感じですかね。
足立:そうすると、教員になられた時に、ご自分が学生だったところから、今度は学生さんと一緒にやるというふうに変わられたと思うんですけど、その時点で何が一番変化として大きかったと思いますか。
馬塚:そうですね。やっぱり私は日本人なので、英語がネイティブではない。もちろん普通に読んだり書いたり喋ったりはできるんですけれども。若い先生だと発達心理学の入門コースみたいな、学生さんが100人いるようなクラスを教えたりします。そうすると、やっぱり学生さんの方も、ネイティブじゃないから、自分が分からないことがあると、先生の英語が下手だからわからないに違いないみたいなコメントもあったりしました。やっぱり授業を色々準備するというのはものすごく大変でしたね。
足立:研究面では、いかがでしたか。
馬塚:研究面では、私の場合は割と早いうちにNSFとかNIHから新人のAssistant Professorにとっては大きなグラントが取れました。博士論文の時から日本語と英語を比較するという研究をしていたので、その延長でアメリカにいる間は英語でデータを取って、夏休みとかサバティカルとかを利用して、日本に来て日本語のデータを取るみたいなことをしていました。お金が取れたのも日本語と英語を比較することを目的とした研究でしたので、そのお金を使って日本の共同研究者達と一緒に仕事をしたり、夏休みなどを一生懸命使って日本に来て、日本で実験するみたいなことをしていました。私の学生さんに日本人はあまりいなかったので、韓国人の学生さんだったり、アメリカ人の学生さんだったりで、彼女達と興味をすり合わせて、色々プロジェクトを作っているみたいな感じでしたね。最初の頃は。
大学教員として
足立:そうすると、若い学生さんとすり合わせる時に、何か先生が工夫された点とかありますか。
馬塚:そうですね。例えば韓国人の学生さんの場合には、彼女も英語のネイティブではないところは私と共通なんだけれども、彼女は韓国語のネイティブスピーカーなので、例えば韓国語と日本語を比較するプロジェクトをやるだとか、英語と韓国語と日本語で、こう三角にして何かやるですとか。だから彼女が得意なことと、私が得意なことと、それからアメリカにいるというその地の利を使ってやるみたいなことは色々工夫しました。
足立:若い方が初めて教員とかPIになった時に、学生さんやポスドクの方に来てもらうのがなかなか大変だみたいな声もあるんですけれども。
馬塚:そうですね。やはり学生さんを採る時に、多分、大学によっても学部によっても違うと思うんですけれども。私がいたデュークの心理学科は、割と若い教官が頑張れるように配慮してくれるというか、優しい環境でした。シニアの先生達は自分達が結構大きなグラントを持っていて、そのグラントで学生さんだけじゃなくてポスドクを雇ったりできるので、外部資金がなくても平等に学生さんを2人ぐらいは学部がサポートしてくれるシステムになっていました。なので、最初の頃は非常に助かりました。なにしろ私のやっている研究のメインが日本語と英語の比較なので、英語しか知らない学生さんに興味を持ってもらうのは難しいトピックでした。ですから、日本語やその他の外国語の獲得に興味がないと、なかなか来てくれる人がいないという苦労もありましたね。でも、デュークの場合は学部の学生さんの中に非常に優秀な人がいて、そういう学生さんに巡り合うと嬉しかったですね。日本の大学だと皆さん卒論書くじゃないですか。デュークの場合だと卒論を全員書かなくても良いのです。例えば心理学専攻で、自分は卒論を書きたいと言うと、そのための準備をして、申請が通ると卒論を書いてもいいよ、という感じなんです。そのような経緯で指導した学生さんがとても優秀で、その一人が今はカナダの大学の先生になっていて、今共同研究をしています。まあ色々できることをできるなりにというか、そういう感じですかね、はい。
足立:学生さんを惹きつけるために、当時、馬塚先生が何か努力されたことはありますか。
馬塚:そうですね。割と優秀な学部生がいる大学の心理学部や言語学部の先生達に声をかけて良い学生がいたらデュークを薦めてもらうとか。後は、応募してきてくれる人の中で、良さそうな人に積極的にこちらからコンタクトを取ったりとかしました。大学院生を採る時には、書類審査に通った応募者の面接をするのですが、そこにこの応募者を呼んでもらいたいと担当の教授に頼んだりしました。でも私の場合は他の先生達に比べると、院生さんの数はやはり少なかったです。私自身が夏休みとかサバティカルとかを利用して日本に行ってたりすることが多かったので、あまり学生さんが大勢いてもお世話しきれないので。まあ良し悪しですよね。
足立:良さそうな方っていうのは、どのように。書類から読み取ったり、面接で??
馬塚:書類からはなかなか読めないですね。デュークは医学部が有名なので、同じ心理学でも臨床心理学の応募者がものすごく多いんですよね。全部で4人とか5人ぐらいしか採らないところに500人ぐらい応募者が来たりします。それにつられて、他の領域もすごくレベルが高くなっています。そうすると、例えば臨床系の応募なんかは、足切りというと変ですけれども、書類審査の段階でGPA、学部の時の成績の平均全部Aだと4.0なんですけど、4.0で足切ったりするんです。だから、4.0が大前提で、それ以上の人ばかり。後は例えばGREとかそういうスコアもあるけれども、そういうものもほぼ満点で。学部を出てからどこかの先生の所でアシスタントをしてパブリケーションがある人だったりとか。そういうレベルの人達のコンペティションになっています。そういう人達から出てくる書類は皆ある程度のレベルになってしまうので、なかなか難しいですよね。かえって、割と小さな大学から、こなれていない本人が書いてくるようなレターなんかだと、読んでいて、「あ、これは何かこの人、自分の頭で考えているな」とか、そういう感覚はあります。授業を教えていて、学生さんにペーパーとかをたくさん書いてもらうと、やはりよく考えている人はなんとなく分かります。多分、皆さん、日本でも同じだと思うんですけれども、同じことを同じように書いているようでも、読んだらやっぱり違うので、やっぱり光る人というのは出てきます。1学年にそんなにたくさんいるわけじゃないですけれども。先ほど言った、昔の私の指導生は、あの学年で何百人の論文やペーパーを読んだ中で、もう格段でした。もう学部の3年生の段階で書いているタームペーパーが、その辺の院生なんかよりもずっと、優秀でした。そういう人達にはやっぱり惹かれますよね。なので、何をもってと言われると難しいですけれども、やはり、「あ、この人はちゃんと自分の頭で考えて、探究心もあって、目の付け所もいいな」とか。何て言うんですかね。難しいんですけれども。センスがあるなっていうんですかね。それは何か読んだら分かります。
問題を抱える学生の指導
足立:なるほど、ありがとうございます。その中でも、やっぱり近い距離で仕事をしていくうちに、ちょっとなかなか上手くいかなかったなぁみたいなものは。
馬塚:それはもちろんたくさんありますね。優秀な学生さんだったけれども途中で(辞めたなど)。大学院生同士がお付き合いしていて、パートナーの就職が決まって、私はもうマスターで十分だから一緒についていくと言って辞める場合ですとか。研究をやってみたら、やっぱりちょっと自分が向いてないと思うって言って辞めていく人も結構いました。自分が向いていないと思ったら、早いうちに辞めた方がいい。辞めると言ったら変ですけど、気がついたというのは大事なことだと思うので、それはいいことだと思うんですけれども、そういう人はいましたね。私の指導生の中でも何人かいて、とりあえず修士だけ取って、「もうこれで十分で、私はこういうのは向いてないと思います」というようなことを本人から気がついて言ってくれる方がいい。こちらが「あなたは向いていないと思うよ」と言うのはとてもつらいので、その方がいいかなというのはありましたね。日本とはちょっとシステムが違うというのもあるかもしれませんが、アメリカの大学の学部は、日本でいうところの、いわゆる受験校の高校、有名受験校みたいな感じなんですよね。学部の時に一生懸命勉強して良い成績を取って、良い大学院に行くために。例えば医学部でも法学部でも、いわゆるMBAとかもみんな大学院なので、学部の時に良い成績を取っていないと入れない。学部に入って一生懸命勉強することがその後の人生を決めるので、皆すごく受験生みたいになっている。そうすると、例えばデュークなんかは医学部が有名なので、PreMedというのですが、自分は将来、医学部を目指すという学部生がすごく多いんです。だけどやっていくうちに、何か自分がPreMedになりたかったんじゃなくて、親が自分にPreMedになってもらいたかったみたいな感じで、やっているうちに、いや、実は自分はもっと文学やりたいんだとか、哲学やりたいんだとか、そういう感じでこう進路が別れていく人もいる。そうではなくて何となくあんまり考えていないけれども、大学の成績が優秀だったら、そういう人は皆医学部に行くもんだ、みたいな感じで、医学部行ったりとか。そのままの流れで例えば心理学の博士に来ちゃう人というのも一定数いるんです。すごく良い大学、例えばイエール大学で、すべての科目で4.0の全Aの成績を取って、イエールで心理学で全Aだったら大学院に行くんです皆、みたいな。だから私も来ましたみたいな感じ。でも、自分が本当に研究者として、向いているか。デュークの大学院は基本、博士を目指す人しか取らない。修士で辞める予定の人は取らない。(修士課程を)やっているうちにもう修士だけでいいと判断して修士を取って卒業する人もいる。でも大学院は、基本将来研究者になる人向けのプログラムです。でも入ってみたら、いや、ちょっと思っているのと違ったみたいな。学部だと言われた宿題を言われたようにやって、期末のペーパーを書いて、良い成績を取っていれば、それでトップじゃないですか。でも段々そうではなくなる。自分で考えて、自分でトピック見つけてみたいなことは、自分は実は向いてないな、みたいな。言われたことを完璧にやるのは得意だけど、みたいな人は意外といる。そういう人達は、授業の成績は良くてもその後が苦しくなっちゃうことがあるように思います。多分、同じ大学院でも分野によって違うと思います。例えば、医学系とか理科系の研究だと、もちろんノーベル賞を取るとか、そういうレベルのブレイクスルーみたいな研究は別ですけれども、領域によっては今これが分かったので、次は何をしなくちゃいけないかというのが、割ときれいに見えている分野もあります。そうすると、そんなに自分で新しいトピックを見つけるぞとか、こういう研究やりたいんだとか考えなくても、次やらなくちゃいけないのはこれだと分かっていればそれを頑張っていけば論文がちゃんと出るような仕事の仕方もあると思います。それが悪いというわけじゃなくて、分野にもよるし、人にもよるし、まあ色々あるのかなと思います。
足立:学生さんや若手研究者が、実は研究に向いていないかもしれないのに、ご本人が気づいていない時に、馬塚先生はどのように?
馬塚:色々ですね。例えば、もっと違う所に行った方が伸びるかもしれないなと思う人もいても、とりあえず今やっていることでうまくいっていて、本人がこれが自分がやりたいことだと思っていれば、まあそれはそれで頑張ればいいというのはあります。でも、本人はすごく頑張っているんだけれども、何かぐるぐるしていて、トンネルを抜けれないみたいになっている人というのも時々いる。そういう人達には、言った方がいいのかなと思う時には言うようにしています。それをポジティブに受け取れるかどうかは、その時の本人の状態であったりとかもするので、なかなか難しいところはあります。例えば大学に行っていて、ちゃんと授業に出て、課題の論文とかプロジェクトとかをちゃんと締め切りまでに出せるかどうかとか、そういうようなことができないのに、自分はこういうことがやりたいんだと言って、授業にもあまり出ないで、自分がやりたいことだけをすごく一生懸命やっていて、すごく上手なプログラミングができたりとか、そういう人がいるわけじゃないですか。そういう人が自分は、例えばサラリーマンになったりとかそういう就職は向いてないので、研究者になりたいって言った時には、結構私も時間をかけて叱りましたね。確かに自分が好きなことにのめり込んで、それが好きというのはいいけれども、研究者というのはそういうことをしなくてもいいと思っているんだったら、それは大きな間違い。自分の指導教官の大学の先生をよく見てみろと。(笑い)学生さんを皆面倒見て、学生さんの就職の世話をして、推薦状もちゃんと書いて、授業も教えて、教授会にも出て。そして、それを一生懸命、毎日毎日ちゃんとこなしていかなければ、研究室が回っていかないし、あなた達みたいな学生さんが困るでしょって。あなたが一番信頼しているあの先生が、普通に大学の先生になった時の研究者の、とても優秀な先生だけれども、(研究者の)普通のパターンですよね。あの先生が、今日は自分の研究がノッているから、授業なんかサボって、朝まで研究しているとか、そうなったら、あなた達はどうなると思っているんだ。今あなたが言っているみたいに自分はあの先生の、あんなつまんない授業よりも、自分のこのプログラムを書き上げる方がずっと楽しくて、良いプログラムができるんだから、これをずっとやりたいわけだから、研究者になりたいというのは、見通しが甘くて、そんなもんじゃないよ、みたいなことは言いました。基本的な、お給料をもらうためにやらなくちゃいけないことをちゃんとできる見通しがなくて、好きなことだけやりたいんですと言って研究者になっても、そんな風にして生きていかれる研究者なんていうのは、よっぽど家が億万長者で、研究費も出してくれて、就職もしなくても良くってというなら別だけれども、なかなかそういうわけにはいかないので、それは多分思い違いなので、よく考えた方がいいよという話はしましたね。はい。泣いて怒ってましたね。
足立:叱りましたとか、怒ってましたとか、おっしゃって。どんな感じで対応されたのかと、ちょっと想像したんですけれども、割とこう論理立てて?
馬塚:そうですね。人それぞれですよね。きっとその叱り方もね。私ももうそんなに若くはないので、今さら、こうね、柄にないことをしようと思ってもできないので、もう思ったことは言わないと伝わらないしっていう感じですよね。はい、しょうがないです。
足立:学生さんや若手の方と、結局、お互いに納得できずに、みたいなことはありましたか。
馬塚:はい、もちろんです。それはよくあると思います。私の方は、例えば納得して、他の研究室や大学に移ったのかなと思っていても、相手の側はそうじゃない人もきっといるだろうから。たくさんではないかもしれないですけれども、あると思います。
大学での研究室運営
足立:ありがとうございます。そしてデューク大学でLecturer、Assistant Professor、Associate Professor、Research Professorとキャリアを積んでいかれたんですけれども、その間に徐々に自分のラボのメンバーも増えていった感じですか??
馬塚:そんなことはないですね。デュークにいた間は、Ph.Dの学生さんを同時に一人以上持っていたことはないです。博士の学生さんとマスターの学生さんとか、学部の卒論を書いていますとかいう学生さんとか(が同時にいたこと)はありましたけど。デュークのラボが大きくなるということはあまりなくて、日本で共同研究をしている先が段々増えてきたというか、海外の共同研究先が増えてきたとかそういう感じですかね。
足立:そうすると、自分のラボでポスドクを雇うということは、その時代はなかったですか?
馬塚:なかったです。そういうお金はなかったので。
国際共同研究を展開する
足立:距離の離れた共同研究相手が多分多かったのだろうと思いますけれども、その時に、馬塚先生の工夫されていたことってありますか。
馬塚:そうですね。私の場合は基本、日本にいる、日本で研究室を持っている同僚達のところにたまに行かせていただいて、そこのラボの施設とか学生さんとか、ちょっと保育園に行くとか、そういう感じで研究をさせていただいていたので、共同研究相手がとても多かったです。とても良い方達に巡り合えて、色々よくしていただいて。少しずつですけども、研究進んできた。そういう感じですかね。
足立:共同研究先を見つけるコツとかありますか。
馬塚:それは芋づるです。どこか1カ所、共同研究をしてくれる人がいると、そこの研究室の他の学生さんだったりとか、その人達のお弟子さんだったりとか、そういう所から色々広がっていくというのはあったと思います。
足立:広げる時にあんまり広げすぎても、多分コントロールが効きかなくなりますよね。
馬塚:そうですよね。その時に自分が何をやりたくて、どのくらいのことができるかみたいなものとのバランスだと思います。有名人が声を掛けてくれたからといって、やたらにニコニコしてついていっても、ちゃんと対応ができなかったら仕事にならないし、というのはあると思います。あんまりこうホイホイ行って、ちゃんと仕事ができないと相手の迷惑にもなるので。そこはやっぱりちゃんと、ギブアンドテイクの形になってないと共同研究ってどっちかだけがおいしいと続かないので。それはやっぱり、相手にも迷惑が。相手にもメリットがあるような形での共同研究しか続かないというのはよく分かっているので、そういうふうには気をつけていました。
国際共同研究のマネジメント上の苦労
足立:共同研究とかで何か失敗したなとか、こうすれば良かったなみたいなことはありましたか。
馬塚:それは色々とありますね。ある意味知らない方と新しく共同研究をするっていうのは賭けでもあるので。大半の場合は、とても良かったけれども。すごく有名人の方が学会とかで寄ってきて共同研究しないかと言われて。それで共同研究をしてみたら、すごく良かった方もいれば、ん??という経験もないわけではなくて。運なので合う合わないみたいなこともあると思うんですけれども。それはしょうがないと思います。デュークの時は、私はアメリカの大学がベースなので、いくら日本の方と揉めても帰る所はあるじゃないですか。しかも海外の大学にベースを持っている人なので、割とちょっと例外扱いみたいな所、許される所もあるんです。私が見ていた感じだと、やはり言語の研究だと、色々な言語を比較する研究というのはとても面白いので、皆さんやりたがる。私は自分が日本人なので、日本に来てやる。日本人ではない先生方が日本に来て、日本語のデータを取りたい時に、日本から出たことがなくて、海外の方とやり取りしたことがない先生が、海外の先生に、言い方は悪いですけれども、目をつけられるみたいになることがある。そうすると、日本の先生が海外の有名な先生の手下みたいな感じで、自分がやりたいことを、全部あなたこれをやっておきなさいみたいな感じでぽんと振られてしまう。こちらの都合も(考慮)なく、結構労力だけ提供させられるみたいなことになってしまった先生方も意外と多い。イヤと言えないというか、どうやってイヤって言っていいか分からないみたいな感じだったりする。また、日本側で共同研究を受け入れた先生が、日本のいわゆる大御所の男性の偉い先生だったりする。学会長とかやっている先生が、海外の有名人から声をかけられて、こういう研究したいんだけどと言ったら、じゃあ僕が見繕っておきますとか言って、自分の手下じゃないですけど、君、何々先生から共同研究のお声がかかったので、とても名誉だからやっておきなさいみたいな感じで振られると、もう断れないですよね。そういう感じで振られて、自分はこの夏こういう研究しようと思って色々準備していたのに、突然その有名な先生から、ポスドクから装置から全部送られてきて、この実験をしてデータをこれだけ取って、結果だけ寄こせと言われた。もうしょうがないから自分の研究プランは全部キャンセルして、その夏は、それだけを全力でやって帰っていただきましたみたいなことを知り合いから聞いたことがあります。その後、私も割と年齢が上がってくると、今度は日本語の研究をしたい海外の先生が私の所に来ることが増えてきました。日本語の成人を対象にしてこういう研究をしたいんだけれど、れい子の所に行ってもいいかと言うから、いやいや、うちに来られても赤ちゃんはいるけれど、大学生はいないから、うちに来てもなかなか進まないよ。じゃあできる人を紹介してくれと言われた時に、知っている人だし割とリーズナブルだと思っていた人なので、知り合いの大学の先生を紹介したら、とてつもない量のデータを、自分達がアメリカで2年かけて取ったようなデータを、日本語はひと夏で取れみたいなことを言われて、ものすごく大変だったっていう話を後で聞きました。私はそれを知らなかったので、平謝りに謝りました。私に頼んできた先生に聞いてみたら、自分の大学は倫理審査とか学部内の制約とかで時間がかかったけれども、日本ならそんな制約はないだろうから簡単にできるだろうと勝手に思い込んでいたらしいことが分かりました。更に、私からの依頼でその依頼を受けた側の先生が、私が間に入ってたから断れなくてみたいな。それはものすごく申し訳なかった。受けた側の先生は(当時彼よりもシニアな立場にあった)私に対して、頼まれたんだから文句言っちゃいけないと思ってやってくださったんだけれども、実は結構被害者になったりとかして。そういうことに気がついてからは、誰かに頼まれた時に、うちで受けるかどうかはまた別として、紹介するにしても、こういう条件を守ってくれないと絶対紹介しないよとうるさく言うようになりました。日本の先生だって、色々制約の中で仕事をしているんだから、このぐらいはできるけれども、これ以上はしない。これだけやると言ってきたんだから、日本に来た学生がこういうことは自分でやらなくちゃいけない。もし計画では何人分データを取りたいと言っていたとしても、こちらで最善の努力をしてもそれが取りきれなかった時に、自分は忙しいから帰るけど、あんた達残りをやっておいてみたいなことは絶対やらないとか、そのようなことをちゃんと明文化して、これがのめるならば紹介するということをするようにしています。海外の先生達も、別に皆が皆、無体なことをしようと思っているわけではなくて、言われないから簡単にできると思ってしまっていた。でも受けた人が結構被害を受けたという意識があって、もう二度と海外の人と共同研究したくないみたいなことになっていた。日本人はイヤって言いにくいじゃないですか。でも日本以外でも例えばアジアの女性研究者は、意外とそういうことが多いことも、段々分かってきた。私のタイの同僚だったり、他のアジアの国の女性、特に若めの女性研究者達が、欧米のシニアの研究者達から共同研究しようと言われて断れないから受けてしまったんだけれども、受けてしまった後、散々な目に遭ったみたいなことを結構聞く。いわゆるパワハラですよね。意図的にやっている人はそんなに多くはないと思うんですが、結果的にそれを押しつけられた人にとって、パワハラ以外の何でもないみたいな共同研究になってしまった、みたいなことは割とあるんですね。私の業界が言語の発達なので、女性研究者が多いということもあるのですが、割と被害に遭うのは女性研究者、若めの女性研究者が多いです。多分、国際共同研究じゃなくても、色々な所でイヤと言えない立場の人がつらい思いをするというのはきっとあるんですよね。
足立:それは文化的な背景もありますか。
馬塚:いや、文化だけじゃないんじゃないかと。
足立:ジェンダー的な?
馬塚:結局パワーがある人が、パワーがない人と共同研究をしようと言った時に、対等な共同研究にするためには、パワーがある側の人が相当配慮しないと、弱い側の人にとってみたら、すごく大変になる。例えば今の私が、タイの共同研究者と共同研究をしようと思った時に、私は全く悪気ないのに、言われたことをやろうと思った側がすごく大変な思いをしているみたいなことは、こちらが考えてあげないといけない。どちらも女性で、どちらもアジアでも、力関係が(存在する)。こちらがシニアの男性で、こちらが若い女性だったら、その差が大きくなるので、そういう違いはあると思いますけれども。シニアの女性がもう少しジュニアだったり、年は近くても、例えばこういう研究をあまりやったことがない人と、こうやりましょうと言った時には、弱い側の人がストレスになることがあることを、私ぐらいの歳になったら、こちらがちゃんと気をつけないといけない。意図せずに全く悪気がないのに、結構相手に負荷をかけてしまうようなことにもなりかねないということは、常々考えないといけないと思っています。
足立:目上の人を敬わなければいけないみたいな文化的な話とも、ちょっと違うんですか。
馬塚:違いますね。はい。もちろん、そういうのもあるんですけれども。例えば日本人は、アメリカの人って目上とか目下とかあんまりないと言いますけど、それは全く嘘。例えばアメリカだって、言っちゃいけないこと、しちゃいけないこと、目上の人は言ってもいいけれども、目下の人が言っちゃいけないこと、そういういわゆる暗黙のルールはものすごくしっかりある。これは研究の話とは違うんですけれども。アメリカに住んでいる日本人の女性が一番嫌なのは、昨日アメリカに来たばかりのような日本人の若い女性が、同じ日本人の女性だというだけでものすごく失礼なことを平気で聞くんですよね。先生どうやって旦那さん見つけたんですかとか。彼女は日本だったら、今挨拶したばかりの大学教授の女性にそんなこと絶対言わないと思うんですよね。よっぽど親しい相手で、たまたまそういう話題になるのが自然な時だったなら別ですよ。でも、なぜかアメリカならそういうことが許されると思っている。私だけじゃなくて同じような経験をした人は沢山います。もちろん、男性に不躾なことを言う人がいないわけじゃありません。でも、日本人の男性に不躾なことを言われるのは(残念ながら)慣れているので驚かないだけです。一般的な誤解と言うと変ですけれど、アメリカ人は男女の差とか、上下の関係とかは厳しくないので、思ったことは何でも言っても失礼じゃないみたいに思い込んでいるんじゃないかと思います。アメリカでは、例えば上下関係の扱い方は日本とすごく違うのは確かだと思います。例えば違う言葉を使うとか、お辞儀するとか。でも、アメリカにも厳然とした違いはあって。それが多分ボディランゲージだったり、ノンバーバルの面でものすごく厳しい。私の個人的な感覚からいうと、敬語とかお辞儀とかで表面的に現れない分、日本よりもアメリカの方が厳しいと思います。そして、そういうことを言ったおかげで爪弾きにされるというのも、日本よりもアメリカの方がずっと厳しいと思います。
足立:そして先生はデュークに15年ぐらいいらっしゃって。
馬塚:そうですね。
足立: Professorまでなられて。
馬塚:いやいや。デュークではAssociate Professorで、まだこれからフルになる前でしたね。理研に来たのは。
理研へ
足立:なるほど。それで理研に来られる決断をした理由を教えていただけますか。
馬塚:それは赤ちゃんをやりたかったからです。ずっと言語の発達をやっていたんですけれども、日本にベースがないと、どうしても普段アメリカにいて、時々日本に来て研究をするのでは、赤ちゃんの研究ってできないんですよね。時々来てできることは、例えば保育園とか小学校とか、そういう所に夏休みとかに行ってデータを取らせてもらうみたいなこと。赤ちゃんの研究は、やはりコンスタントに赤ちゃんを募集して来てもらってみたいなことをしないといけないので、できなくて。多分誰でもそうなんですけれど、発達をやっていると最初は少し大きい子供を対象にしてやっていても、段々、もっと若い子をやりたくなるんですよね。言語の発達もやっぱり3歳より上でできることに限界があって、段々もっと下の、赤ちゃんのところからやりたいって、なるんですよね。そういうことを考えていた時に、脳センター、あの時はBSIだったんですけれども、脳を育むという領域ができて、そこでPIの公募があるということを(聞きました)。全然関係ないんですけれども、私がデュークにいる時に、早稲田で修士の学生さんの修論の面倒を見ていました。彼がたまたまBSIでアルバイトをしていて、先生、多分興味はないと思うんですけれども、こういうポジションがあります、と公募広告を送ってきた。私は本当に文系の人なので、当時、理研というと何となくワカメの会社のイメージだったんですけれども。(笑い)それから大急ぎで色々調べて、担当の方に連絡してみたら、ぜひ応募してみてくださいというから、応募書類を出した。色々あったんですけれども、採用していただいて、ここに来ることになりました。なので、私は、言語発達の研究者としてはもう15年ぐらいやっていたんですけれども、赤ちゃんの研究というのは理研に来てから始めたので、その方面ではまだまだ本当中堅どころぐらいのキャリアです。
足立:アメリカの大学で学生さんのお世話をしながらというのと、理研で研究室を構えるというのは、だいぶ違うと思いますけれども。
馬塚:違いますね。それはもうまず第一に、授業を教えなくてもいい!(笑い)私の夫はアメリカ人で、近くにあるノースキャロライナ州立大学の先生をしています。大学によって、そのコマ数、日本の大学もそうですけれど、コマ数とかが違うんです。デュークはすごく恵まれているので、夫に比べると、私はティーチングの負担はすごく少なかったです。それでも100人の授業を週に3回とか、院生のセミナーとかやろうと思うと、教えている間はなかなか研究に割く時間というか、寝る時間を削るしかないみたいに、どうしてもなってくる。ここに来たら授業を教えなくてもいいので、もうそこは全然天国だなと思いましたね。
理研で研究室を立ち上げる
足立:そしてどのようなマネジメントスタイルで研究室をやりたいと思ってこられましたか。
馬塚:いや、それは来てみるまでは見当もつかなかったんですよね。今でこそ、日本赤ちゃん学会というのがあって、赤ちゃんの研究をやっている心理学の先生方も増えてきましたけれども、まだまだすごく少ないです。赤ちゃん研究をやるラボというもの自体が非常に珍しい。だからどういう人をどうやって採って、どうやって動かしていくのか。もう本当に見当もつかないという感じで、とりあえず来て、まあやってみようみたいな感じで来たんですけれど、はい。(笑い)まあ、だめならやめて帰ればいいかとか思っていたんですけど。
足立:ポスドクを雇うのは理研で初めてですよね。
馬塚:そうですね。はい。
足立:その時に気を付けたこととかありますか。
馬塚:最初の頃は本当に分からなかった。CBSの中でラボを移りたいと言っていたポスドクの人達を何人か受け入れて、私の方でも公募して何人か採って、みたいな感じで回ってはいました。何しろ私がやりたいような赤ちゃん研究をやっている先生の学生さんでPh.Dを取った方が外に出てくるということはまずなかった。あの当時多分日本に2人か3人ぐらいしかいなくて、もうその人達は就職していた。そうすると、興味はあるけれど、全然違うバックグラウンドの方に来てもらって、その人達が赤ちゃんの研究ができるように、ラボ自体もそういうことができるように皆を訓練しながらということで、最初の5年ぐらいはもう何か、皆してトレーニングキャンプみたいな感じでしたね。赤ちゃんをリクルートする人を、当時、学芸大学で同業の先生が赤ちゃんの実験をしていらしたので、そこに通ってもらって、そこでどうやってリクルートしているのかを学んできてもらうとか。別のラボから来て、脳波の研究実績がある人をアメリカで赤ちゃんの脳波研究をやっている先生のところにお願いして、丁稚に出してひと月ぐらいいて、色々勉強して帰ってきてくださいとか。別の先生のところで、行動実験をやっている先生の所に学生さんを送り込んで勉強してきてもらうとか、そういうようなことを色々したりとか。また、そういう研究をご自身でやっている先生方にも来てもらって、実験の様子を見てもらうとか、そのような感じで。私だけじゃなくて、ラボのスタッフも皆ゼロから学びますみたいな感じでやっていましたね。
足立:そうすると、ラボが順調に運営できるまで、結構苦労されたということですよね。
馬塚:そうですね。5年ぐらいはかかりました。その間は今よりも脳センターが割と予算的にもゆとりがあって、とても恵まれていた時期なので。伊藤正男先生とか甘利先生とかが(いらした)。私が来た時は甘利先生がセンター長だったのですが、とても太っ腹で、最初の5年ぐらいなんか、あんまり目ぼしい成果も出てなくてあれでしたけれど、とにかく頑張ってね、みたいな感じで言ってくれていたので良かったんです。今のシステムで、例えば来てから7年の間に無期になるような業績を上げなさいとかと言われてたら、私なんかとても無理でしたね。一度ベースができれば、そこからはやるべきことはたくさんあるわけなので、そこから先は論文もたくさん出るようになったし。一旦論文が出れば、後はうちに来たいという人もいるし。海外とも、赤ちゃん研究での共同研究もたくさん動くようになるし、それは順調になりましたけれども。やはり最初の5年間、とりあえずがんばんなさいみたいに言ってくれた、スタッフやセンター長とかがいたので、今あるんですよね。
足立:その最初の5年間を乗り越えるのに、ラボのメンバーの方々も、非常に論文に繋げるところまで大変だったと思うんですけど。
馬塚:そうですよね。最初に来たメンバーで、論文まで繋がらないで辞めてしまった人も結構います。私はその当時はよくCBSのシステムも知らなかった。文系から来た人だし。CBSは基本理系じゃないですか。ちゃんと英語で、もちろん私達の研究なんかはNatureとかには出ませんけど、いわゆるトップジャーナルに論文を出さないといけないという所です。私みたいに心理学でも、海外の大学院にいた人はそれが基準なので別にいいんだけれども。ずっと日本の大学の文学部とかで来た人達というのは、指導教官の先生自身も日本語で本を書いたり、日本のジャーナルに論文を書いたりはするけれども英語で論文を書くことがない方もいらっしゃいます。ことがない人が多くて。そうすると、そういうところで研究してきた人は、突然英語で論文を書けと言われても、どうやったらいいか分からないこともあります。逆にCBSの別のラボから移ってきた人なんかは、これまでねずみの実験をしてたのに、突然ヒトになるじゃないですか。そこら辺の加減もよく分からないとか、何かそういう感じで、皆苦労はしていました。それこそデュークの院生さんじゃないんですけれども、ちょっと思ってたのと違いますと言って、他に移られた方もいた。ちょっと粘って論文を書くまでいた人もいた。それは向き不向きもあったというか。最初に来てくれた人たちがいたからこそ、ラボを立ち上げることができたので、その人達にはもちろん感謝はしています。私も別に、必ず論文何本出ますと言ったわけじゃないし、なかなか難しいところはありますよね。(苦笑)はい。
足立:なるほど。先が、多分なかなか見通しできないような状況で。
馬塚:そうですね、はい。
足立:どのようにラボのメンバーをエンカレッジといいますか、励まして?
馬塚:それは人それぞれというか、エンカレッジなんかしなくても結構皆さん、自分で頑張ってくれる人が多いので。そういう人が中に何人かいると、それ以外の人達は彼らを見ると、そういう風にしなくちゃいけないのかなと思ってくれるようでした。そして、それを何年かやっていて、自分にはちょっと辛いとなったら、ここに残っても辛いばっかりなので、他に行こうかなというふうになるんじゃないかなと思います。良い悪いは別として、企業の研究所に就職したりする人もいて、それはそれで皆が楽しくやっているから。だから皆が皆、大学や研究所のPIにならなくても、人それぞれなので、それはいいんじゃないかなと思うんですけどね。
足立:そうすると、最初の5年間を乗り越えた後は割と順調に?
馬塚:そうですね。はい。2回目の5年間は割と順調に行きました。そこからCBSのシステムが変わって利根川先生がいらっしゃって、あの当時シニアチームリーダーというシステムをお作りになった。たまたま私がシニアチームリーダーに通してもらった。それまでは、私は本務はデュークで給料はデュークからもらっていたんです。理研では立場上、非常勤みたいな感じでラボを運営させてもらっていた。デュークのサバティカルとかリーブとかを利用して、半分ぐらいは日本にいる感じでやっていたんです。だけど、シニアにしてもらったのを機に、デュークからお給料をもらうというのは止めた。デュークではResearch Professorという、お金をもらわないけれども、リサーチ活動ができますというポジションをもらって、理研をメインにして、というのはそこからですね。2013年ぐらいからそういう風にやってきました。基本的に理研の人で、デュークでもアポイントメントあるけど、みたいな感じの立場でやるようになった。
中長期的なプロジェクトを立ち上げる
足立:シニアチームリーダーになられたところで何か変化はありましたか。
馬塚:私の個人的な感覚としては、それまでは今学期はデュークで授業を教えなくちゃいけないとか言うと、半年単位でいなくなるじゃないですか。その間のラボの運営っていうのは結構大変だったんですけど、それをしなくてもよくなった。落ち着いてこちらで仕事ができるようになったのは、やっぱりすごくやりやすくなりましたね。それまでは、もう日々、今月をどう乗り切るかみたいな感じで。多分お子さんが小さいお母さんとかそういう感じなんでしょうけれど、そんな感じで動いていた。ちょっと落ち着いて、色々仕事ができるようになった。ずっとやりたかったんだけれども、手をつけられないでいた大きな縦断研究をやりたかったんですよね。赤ちゃんを例えば何年か続けて、大規模にフォローして少しずつ、たとえば変わっていく間を見る研究をやりたかったんです。あと5年でラボがなくなるかもしれないような時に、そんなことをやっても意味ないので、やりたいけどできないなと思っていた。シニアになった途端にそれを始めて、(笑い)そこからデータを取り終わるまでに大体5年ぐらい(かかりました)。
今、取ったデータを色々解析しているところです。ものすごく膨大なので。700組ぐらいのお母さんと赤ちゃんを、赤ちゃんが5カ月の時に入ってもらって、そこから5カ月、8カ月、10カ月、18カ月、20カ月とずっとフォローして、その後、語彙が出るようになった時の語彙を見て。こういう途中の、どういう変化があるかみたいなことを縦断でフォローするみたいなことを、コホートと言います。そういう縦断研究はシニアにならないうちはできなかったことなので、とりあえず首になる心配はしなくていいということで、(笑い)やっています。
足立:そうすると、ラボのメンバーの数というのも、そこからは増えた感じですか?
馬塚:いや、そんなことはないですね。予算のこともあって。私が来た頃はとても予算も潤沢だった、今に比べると。外部資金とか取らなくても、内部の予算・交付金だけですごく色々なことができました。スタッフの数にも、もっとゆとりがあったんです。でも、段々交付金でもらえる予算が減ってきて、外部資金も取ってくださいって言われるようになった。最初の頃は私達は文系なので、日本で多分、私が一番お金を持っている文系の研究者だったんです。そうすると、他大学の先生達の5人分とか、7人分ぐらいの科研費を、私が一人でもらっているわけじゃないですか、申請もせずに。ですから外に申請するのは申し訳ないので出さないようにしていました。でも段々予算が減ってきて、そうも言ってられなくなった。外部資金も取るようになってきて、しばらく前に(科研費の)基盤のSを取りました。さっき言ったような大きなコホートを作るデータの実験が、とりあえず実験自体は大体片付いたので、次にやりたかったのが日本だけじゃなくて、他のアジアの国を巻き込んでやる共同研究だったんです。今までの共同研究は、フランスとかイギリスとかアメリカとか、そういう国のPI達が私と共同研究して、日本語のデータを取りたいって言って一緒にやって、そういう研究もいっぱいやっていました。それはそれで楽しいんですけれども、やっぱりアジアの国の言語をやっているのが私だけだと、なかなか説得力が出ない。アジアの他の国も一緒にやりたいと言ってスタートしたのが基盤のS。それをちょっと拡張した形で特推(科学研究費助成事業特別推進研究)が取れて、今はアジアの国と欧米を比べる共同研究みたいな形で動いているんです。理研に来てから、ここに腰を据えて研究をやるぞとなると、やっぱりやれることややりたいことのスコープも変わってくる。いくらやりたくてもどうせできないと思っていることに手出してもしょうがない。シニアになって、それから外部資金も「申し訳ない」と思わずに、しっかりガッツリ取りに行ってもいいよみたいになって、そういうことも含めて研究ができるようになってきたので、ちょっと変わってきたかなと思います。
足立:そうすると、ラボの人数はそこまで増えずに。
馬塚:増えてないですね。
足立:共同研究の人がどんどん増えていったという感じですか。
馬塚:そうですね。特推は6カ国の共同研究なので、それぞれのラボの共同研究先に、特推のお金で、そのプロジェクト担当の人を雇ってもらうとか、そのような感じでどんどん増えていく。全くゼロからという人はいなくて、これまで何らかの形で共同研究をしたことがある人たちに集まってもらってやってます。
足立:6カ国となると、結構いろいろな文化とか、その国独自の。
馬塚:そうです、そうです。文化を比較するのが今回の目的。赤ちゃんの言語の獲得に、母子の社会的な関係っていうんですかね。お母さんと子供のコミュニケーションの仕方が、例えば、欧米とアジアではだいぶ違うとか。そういうことが赤ちゃんの時の音声とか語彙の発達とかにどういう影響を及ぼすかというのを見たいという研究なんです。これまでも色々そういう研究はあるんですけれど。単発で例えば、日本とカナダは違うとか、中国とアメリカは違うとか、一対一の研究では何が違っているのかってよく分からない。だから、アジアの言語も複数取って、欧米の言語も複数取って、全部まとめてどこが違うからこうなっているのかみたいなものを色々見たいというのが今回の特推の目標です。いかんせんコロナで、なかなか思うように動いていないんですけれども。
足立:研究の中身も文化的な背景があるというのがびっくりしたんですが、プロジェクトそのものとか、共同研究のスタイルとか、それも6カ国で違ったりしますか??
馬塚:共同研究の相手方は、皆アメリカまたは欧米で学位を取ったりした人ばかりなので、基本、英語でアメリカ風に全部やれるという感じです。一回も海外に出たことがない人というのは一人も入っていない。例えば、韓国で下からずっとという人たちと何かやろうと思ったら、それはそれできっと大変なんでしょうけれども。でも、韓国のラボも元私の教え子です。なので、研究者仲間のいわゆる研究の基準だったりとか、実験の基準だったりとか、そういうものは、割とアメリカ基準で統一しているっていう感じです。
足立:特にストレスなく?
馬塚:いや、もちろん色々(あります)。そんな簡単じゃないので、もちろんそれぞれストレスは、あります。でも気心の知れた共同研究者の集まりで、それぞれ各国でのトップレベルの人達なので、とても恵まれていると思います。
足立:順調にいってそうでも、ストレスがあるいうところに興味を持ったんですけれど、どのようなストレスでしょうか?
馬塚:何でもそうですよね。もし自分の会社で何か製品を作っていたとしても締め切りはあるでしょうし。いつまでに製品を作らなくちゃというのは、もちろんストレスだけれども。でもそれができるから面白いわけで、ストレスが全くなかったら仕事にならない。それはもうしょうがないです。良いストレスというんですかね。何かをやりたいので、それを生み出すための産みの苦しみみたいなのは、ストレスではあるけれども、そんなに辛くない。悪いストレスじゃないんですね。特推の研究は私がお金を出しているので、もちろんお金を出しているのは日本政府ですけれど、私の特推なので、最終的には私がよしと言えばいいし、ダメと言えばダメなわけですよ。ストレスのかかり方は他の人よりももしかすると、少なくともこのプロジェクトに関しては少ないかもしれないです。
特に欧米の共同研究者達は、それぞれ自分のグラントを持っていて、私なんかより大きなグラントを持っている人も何人かいる。だからお金の額が云々ということではない。たまたまこういうことをやりたい人が私で、そのためのお金を私が出す。逆に向こうの人が何かやりたい時に、こっちがデータ取ってあげたこともあれば、そういうこともある。そういう研究相手達なので。まあしょうがないです、ある程度のストレスは。
キャリアのターニングポイント
足立:PIとして一番楽しかったことは何ですか。
馬塚:そうですね、色々、あります。若い時はシンタックスという、言語の文法の獲得みたいなことをやっていたんですよね。ある時から少しずつ、赤ちゃんの研究をやった方が面白いんじゃないかなと思うことがあって、それをスタンフォード大学で開催された学会で発表した時に、気に入ってくださったJusczyk先生という方がいた。Jusczyk先生が私のアイディアを気にいって下さったのが縁で、ブラウン大学の先生が企画していた大きな国際シンポジウムに招待してもらって、そこで発表する機会をいただきました。そのシンポジウムにはそれこそ世界中の赤ちゃんや子供の言語発達の先生方が招待されていて、大勢の方から私の発表が面白かったと声をかけていただきました。あれは本当に嬉しかったです。そこから本格的に赤ちゃん研究をやっている先生方に、声をかけていただけるようになった。
理研に来たのも、その時のシンポジウムがきっかけです。BSIで「脳を育む」の領域の公募があった時に、応募してみたら面白いかなとか思ったんですけれども決断できずにいました。そのころ、たまたま参加した学会で、知り合いの赤ちゃん研究者のJanet Werker先生と会ったので、実はこういう公募があって応募してみようかと思うんだけれど、どう思うかと相談してみました。その時は二人とも別の先生の講演を聞いていて、後ろの方でぼそぼそ話をしていたんですが、Werker先生が「ぜひ応募しろ」って言って、その場で私の手をガって握って。(笑い)トークしていたのは、Jacques Mehlerという、Cognitionというジャーナルを創立した有名な先生です。彼ともブラウン大学のシンポジウムで知り合ったんですが、トークの後、Werker先生は私をMehler先生のところまで引っ張っていって、「Jacques、れい子が理研に応募したいって言ってるから、二人で推薦状を書いてあげよう」とか言って。後で聞いたら、Janet Werker先生は、その当時、BSIのアドバイザリーボードのメンバーだったそうなんですよね。貴雄ヘンシュさんという方がいらして、ヘンシュさんが臨界期に興味を持っていた。もともと言語発達から言語や臨界期みたいなものに興味を持っておられたので、Janet Werkerをボードのメンバーにお願いしたのもヘンシュ先生だったそうなんです。私はそういうことを全く知らなかったので、ちょうどJanetと親しかったので、Janetに相談したら「絶対応募しろ!」と言って、そのJanetが、「じゃあJacquesもれい子のことよく知っているから、推薦状を書いてもらおう」って言って、もうその場で推薦状を書いてくれる方が2人決まった。後で色々話を聞いたら、Janet WerkerとJacques Mehlerからあんな推薦状もらった候補者を落とすわけないと言われて。そうだったんだ~とか。(笑い)だから、その時に招待していただいたブラウン大学のシンポジウムが、その後、私の研究テーマを(決めた)。
子供の文法学習から赤ちゃんの音声発達に、全面的にシフトする。勿論、理論的には繋がっているんですけれども、やっていることはだいぶ違うので、そのきっかけになったあの時の、あの講演というのは、ある意味キャリアの一つのターニングポイントだったんじゃないかなと思います。「れい子のあのブラウンのトークを聞いて話したいと思っていたんだ」というようなふうに言ってくださる方がたくさんいるので、やっぱりあの時の、あの講演がすごくターニングポイントだったんです。もちろんコーネル大学の博士課程の時の指導教官だったBarbara Lust先生が、成績も悪い落ちこぼれだった学生なのに、私を大学院生として採ってくださって、本当によく指導してくださったので、もちろん彼女と会ったのがステップ1です。その後Jusczyk先生と会ったり、Werker先生と会ったのがステップ2で。その経由で甘利先生とか、ヘンシュさんとかに理研に引っ張っていただいて、そこがステップ3みたいな感じですかね。なんか今思うと、すごい超絶ラッキーだなと思うんですけれども。(笑い)
足立:そのステップ2の先生方にはどうやって知り合ったんですか。
馬塚:Janet Werker先生とJacques Mehler先生と個人的に話をするようになったのは、そのブラウンの学会がきっかけです。一番最初に私が結構理論的なペーパーをスタンフォード大学の学会で発表した時に、Peter Jusczyk先生という、赤ちゃん研究ではとても大御所の先生が、たまたまその学会のキーノートでいらしてたんです。私はそこに普通に応募して、自分で発表したんですけれど、Jusczyk先生が私のトークを聞いて、すごく面白いので一緒に何かやらないかって言ってくださった。それから時々、当時先生がBuffaloにいて、その後Johns Hopkinsに移られたんですけれども、時々行って話をしたりするようになったんです。私はアメリカにいて、デュークにいるので、なかなか日本の赤ちゃんの実験はできない。でもJusczyk先生が、日本人の赤ちゃんで実験できなくても、日本語の刺激をうちのラボで英語の赤ちゃんで実験してみればいいじゃないかって言ってくださって。いくつか(実験を)やっていた。
その繋がりでブラウンで学会があった時に、Jusczyk先生は妥当に自分の研究で招待されたんだけれども、実はこんな面白いことをやっている人がいるから、れい子も招待してやってくれと、ブラウンの先生達に頼んでくださった。そこに結構、その分野ではとても偉い人たちがたくさん来ていたみたいで、私のトークにオーディエンスとしていらしていた先生達がたくさんいた。中でもJusczyk先生以外にはJacques Mehler先生とJanet Werker先生がすごく気に入ってくださって、その後ラボにも呼んでくださったりとか、フランスのJacques Mehler先生のラボに夏3カ月ぐらい見ていただいたりとか、そういう感じで知り合っていたので、そういうところに理研の話が出てきた。もちろん知らなかったわけじゃないんですけれども、何かそうやって繋がっているんですよね。不思議なものです。
PIとしての苦労
足立:PIとして一番楽しくなかったことは何ですか。
馬塚:PIというからには、理研に来てからですよね。理研の組織内の話だったり、そういうことで。私もそうですけれども、同じPIの先生方がどんどん疲れていくというか。分かります??研究じゃない所で、色々制度が変わったとか、新しくこういうことをしなくちゃいけないとか、予算が減ったからこうしろとか、そういうので色々少しずつ変わってくるじゃないですか。長い目で見たら必要なことなのかもしれないのですが、先生方がどんどん疲れていくというか。委員会とか、色々書類を書くとか、そういうことの方にばかり時間を取られてしまって。個人的に例えばご飯食べに行ったりしても、そういうことの愚痴ばかりになっちゃうみたいな。以前はそうじゃなくて、もっと楽しいこととか、「この間学会でどこそこに行った時にこんな楽しかった」とか、「こんな面白いことがあった」とか、そういうことがもっと多かったんですよね。段々予算がきつくなってきたこともあるんでしょうけれども、予算をちゃんと理研からBSIにつけてもらうには、こういうことをしないといけないとか。多分、必然的なものなんだろうと思うんですけど、そのために色々研究とは違う所で、あんまりきれいなことばかり言っていられないよ、みたいなことに割かないといけない時間が増えてくればくるほど、皆ストレスが溜まってきて、何か楽しくないなという時期はありましたね。
足立:楽しくない時期をどのように乗り越えられましたか。
馬塚:仲の良い人達と集まって愚痴をこぼしまくって、生き延びましたね(笑い)。温泉に行くとか、おいしいものを食べるとか、そういう感じです。それはたぶん皆同じだと思うんですけど。
足立:ラボのメンバーの方には?
馬塚:あまり関係ないので、PI会議で来年の予算のタマ出しの話などは。そういう話はあまりラボメンバーの人に言っても、負担になるだけ。色々なことをなるべく秘密にはしないようにしています。例えば、私が今年シニアの審査を受けるので、これで通るか通んないか分かんないけれど、ここで通らなかったら、ラボは後2年ぐらいで閉まる。そうなったら皆さんその先のことを心配しなくちゃいけないよとか。来年の予算がこういう風になってきたから、すごく厳しいんだとか。そういうようなことはなるべくラボの人たちにはオープンに伝えているつもりではある。でも細かい、あの先生とあの先生が仲が悪いとかいう話はあんまりしてもしょうがないので。(笑い)PI同士で愚痴をこぼし合って生き延びるようにはしていました。
足立:ありがとうございます。では、ひとまず私からは終わりです。松尾さん、何かあればお願いします。
松尾:馬塚先生にとって、PIを目指すことと研究者を目指すことは何が違いますか。
馬塚:どちらもあまり変わらないかな。私自身は、PIではない研究者をやったことがないので。大学院を出て、そのまますぐ大学のいわゆるテニュアトラックのAssistant Professorになっちゃったので、もうその時点からPIじゃないですか。だからポスドクというのもやったことがないので。学生の時に先生のグラントのRA(Research Assistant)をするとかいうことはありましたけど。ポスドクをしたことがないのでよく分からないですね。今の若い研究者の方はそういうことがあると思うんですけれども、あの当時は、私達みたいな分野はポスドクという概念がなかった。
松尾:ありがとうございました。
ワークライフバランス
足立:先生のワークライフバランスといいますか。仕事とプライベートはどのように。
馬塚:仕事ばかりの時は朝から晩まで仕事をしているし、もう何かイヤになると、しばらくあまり仕事のメールは見たくないみたいな時もあるし、あんまりバランスが取れているかどうかはちょっと。(笑い)もう小学校1年生の夏休みの宿題からそうなんですけど、本当に締め切りギリギリにならないとやらない人なので。ギリギリになると泣きながら、もう本当に食べる時間も寝る時間も削って「わーっ」てやるんですけど、いったん喉元過ぎるとまたすっかり忘れて、また「パーッ」としてて、また締め切りが来ると「わーっ」となるっていう、そういう感じ。トータルで言うと、他の方と同じように、ワークライフバランスが取れているんだろうと思うんですけど。なんかこう時期によってこうって感じですよね。でも私は子どもがいないので、それでこんな風でも何とかなっていたんですね。子育てをしている方達を見ると、そうはいかないので、どうしてもやっぱり1日の中で、きっちり進めていかないといけないから、そういう風になるので。もし私もそういう状況にあれば、きっとそうなっていたと思うんですけど。幸か不幸かそういう状況になってないので、いつまで経っても小学校の夏休みの宿題と同じだなと思いながら、泣きながら締め切り前の、夜中の2時とかに論文を直していたりとか、するんです。(笑い)明日までに出さないと査読に間に合いません、みたいな。
足立:ラボのメンバーの方のワークライフバランスはどのように?
馬塚:多分、うちのラボメンバーは、比較的、私よりはずっとバランス取れていると思います。産休を取ったり、育休を取ったりした人のサポートの予算があったじゃないですか。その応募者数が、圧倒的にうちのラボの人が多くて。(笑い)私、少子化対策何とか本部から報奨金を貰いたいなと思うぐらい、うちのラボの皆さんは、結構(多い)。うちは赤ちゃんの実験なので、子育ての経験のある方が戻ってきてくださった時に、実験者として一皮むけるんですよね。だから、子育て経験のある方は大歓迎なので。そういうこともあるから、うちのスタッフは、例えばもう一人子供を産むというのも積極的だし、それをサポートする雰囲気も周りにもある。もう5時とかに皆パーッと帰っちゃうから。だから、いつもこう部屋閉めて帰るの私だし、一番最後に。(笑い)おうちで休んでいるかと言われると、きっと子育てとかで、ご飯の支度とか、保育のお迎えとかで、めちゃめちゃお忙しくしていらっしゃるし、皆していると思うんだけれども。仕事の外にちゃんと私生活があって、それを守りながら暮らしているという意味では、バランスは比較的取れている方なんじゃないかなと思います。CBSの中でも、本当に夜までラボに煌々と電気がついていて、PIもポスドクも皆いるみたいなラボもたくさんあるけれども。うちは実験はどうせ夕方過ぎたら赤ちゃん来ないし、皆さんお子さんいるから帰らなきゃいけないし、みたいな感じで、割と夕方になったらスパッと帰っちゃうと思います。私が言っているだけか?
足立:PIとしても、そういう雰囲気を大事にしてますよっていうマネジメントなのですね。
馬塚:そうですよね。子どもが苦手な人とか、子どもが来た時に、ギャーギャー泣いたりとかいうのが気になっちゃうような人は、こんな所では生き延びれない。どうしてもそういうのが好きな人とか得意な人とか、最初得意じゃなくても段々得意になっていく人とかがやっぱり多くなるんじゃないかなと思います。初めてうちのラボに来た時にまだ独身で、とても優秀な研究者の人がいて、彼がニルズ(Near-Infrared Spectroscopy:NIRS)という脳の計測をやったんですけど、彼が出てくると、赤ちゃんに泣かれると言って、スタッフに一時期、「部屋の外へ出ててください」とか言われていたんですよね。でも、結婚して子どもが生まれて、しばらくしてフルに復帰してきた。「すごい、赤ちゃんに泣かれなくなった」と皆が言った。きっと何か、服とか、ミルクとかそういう匂いが付いているんだろうとか言ってました。本当に匂いなのか、本人が自分の子どももいるので、被験者さんに対してちょっと柔らかくなったのか、そこら辺はよく分からないんですけど。彼なんかは、最初は苦手だったけれども、自分が親になっていく過程で、段々慣れてきた。そういう人もいるんですけどね。
足立:それでは、最後に、馬塚先生の、PIとしてラボを運営するポリシーというか、こういうふうにやってます、みたいなのをお聞かせいただけますか。
馬塚:私がやりたいことが基本で、プライオリティで動いているのはそれまでなんですけれども、それぞれの研究員のバックグラウンドを利用するというんですかね。生かせるような、なおかつ、うちの研究にフィットするような形で、その研究のテーマを決めて、動かすというのが、多分うまくやるための最低条件なのかなというふうには思うんですね。ただ、なかなかそうは言っても、一人一人の研究員さんがやりたいことのプライオリティが、私がどうしてもやらなくちゃいけないこととのバランスで、ちょっと私の希望の方が通ってしまうことの確率は多分、高いのはしようがないだろうなというふうに思うんですけれども。でも少しずつそういう感じで、皆同じことをやるのではなくて、この人はこういうのが得意なので、これをやってもらうみたいな感じで、こうやるというのは、一応意識はしているんですけど。その通りになっているかどうかはまた、別の問題です。はい。
足立:どうもありがとうございました。
インタビュー実施:2022年6月28日
インタビュー場所:情報基盤研究棟411室
RIKEN Elsevier Foundation Partnership Project
撮影・編集 西山朋子(脳神経科学研究センター)
撮影支援・編集支援 雀部正毅(国際部)・小野田愛子(脳神経科学研究センター)
インタビュアー・製作支援 松尾寛子(ダイバーシティ推進室)
インタビュアー・製作 足立枝実子(ダイバーシティ推進室)